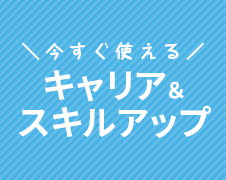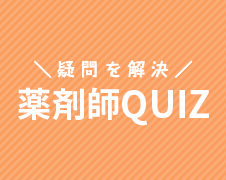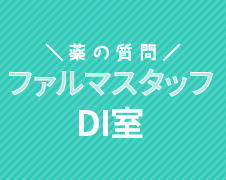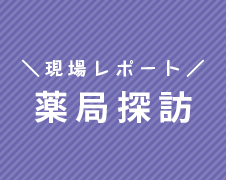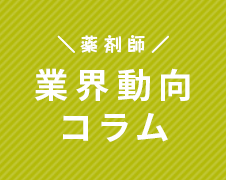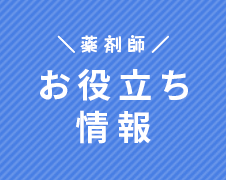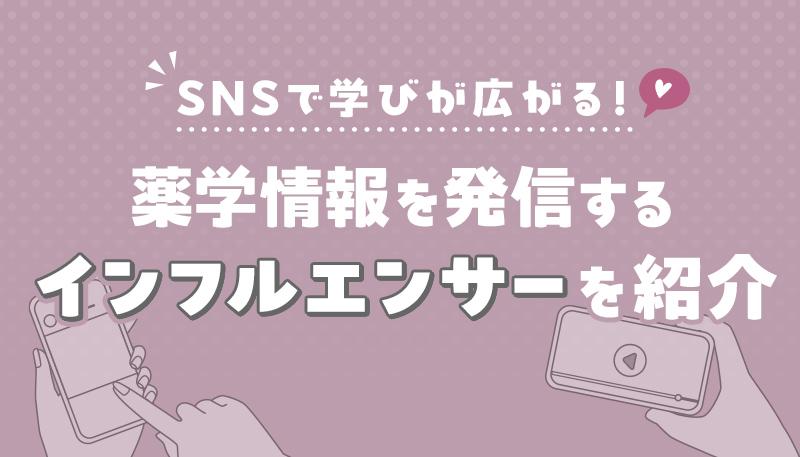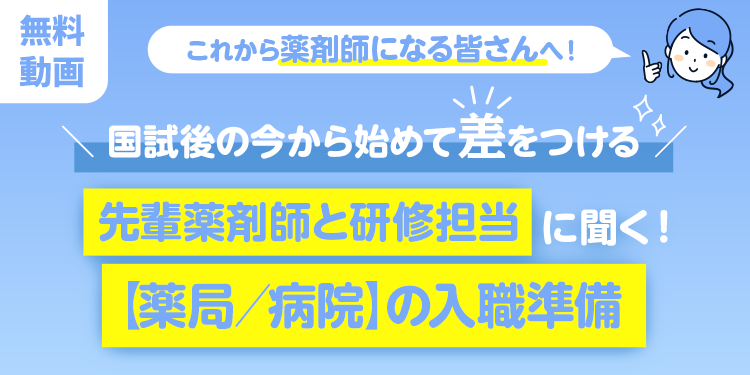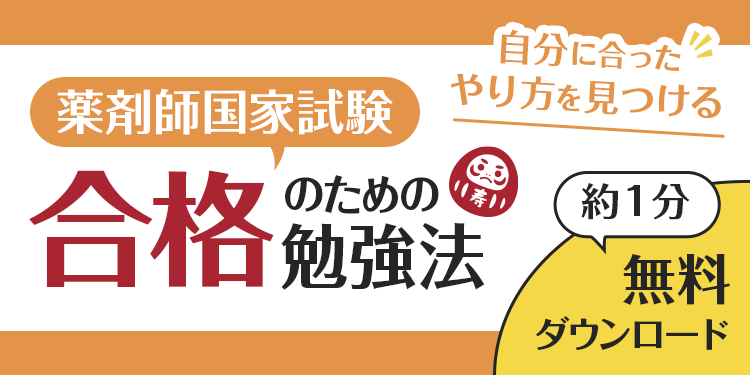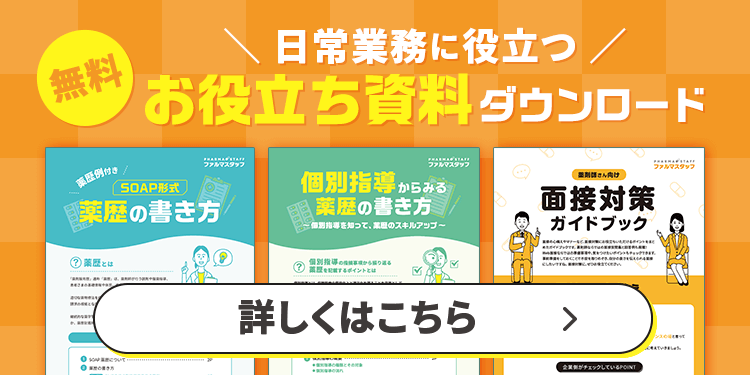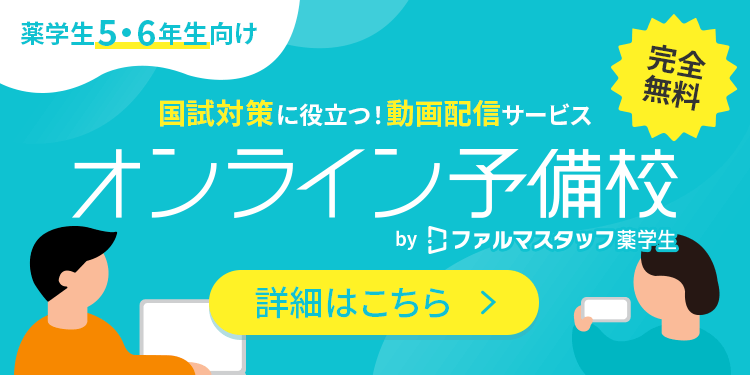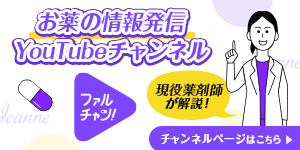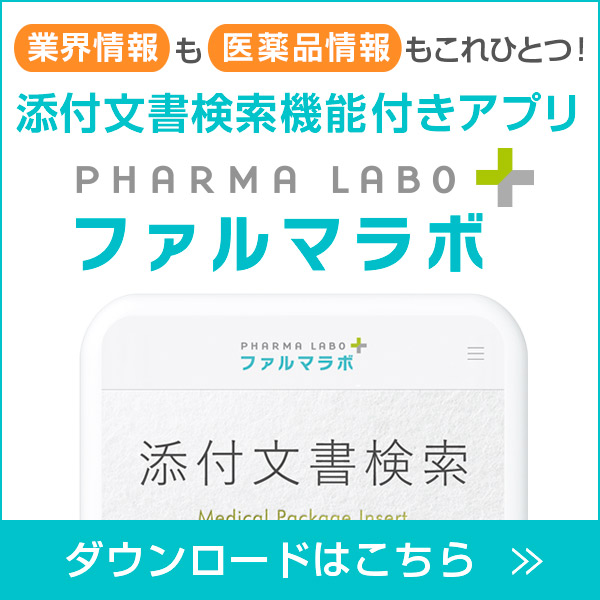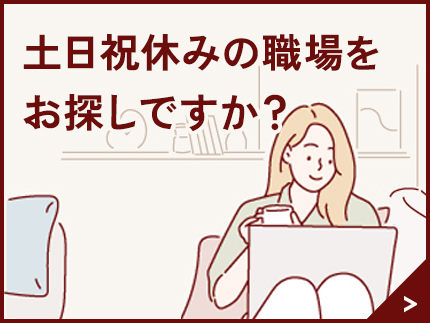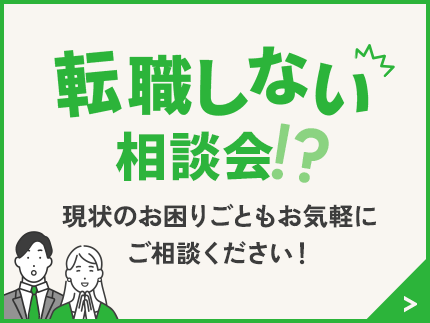- 公開日:2019.01.11
- 更新日:2025-03-05
若手薬剤師の必読書。スキルアップに役立つおすすめ本9選

「薬剤師としてもっと知識を増やしたい」「キャリアアップのために勉強をしたい」という場合には、本を読むこともおすすめです。
今回は、転職や同じ職場でのキャリアアップを経験した先輩薬剤師の方に、「ぜひ若手の薬剤師に読んで欲しい!」という本を選出してもらいました。今後のスキルアップのためにぜひ参考にしてみてください。
知識を増やしたい薬剤師におすすめの本
1:誰も教えてくれなかった実践薬歴 改訂版(山本雄一郎)
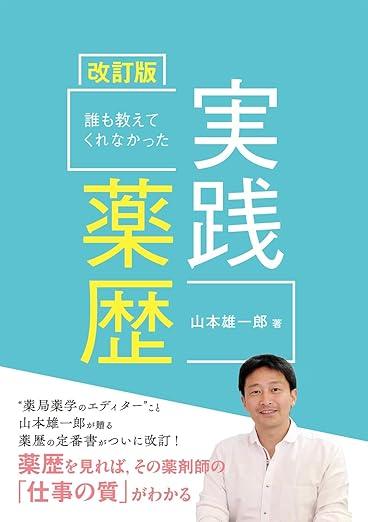
- 著者:山本雄一郎
- 出版社:じほう
- 発行年:2024年
薬剤服用歴(薬歴)は、薬剤師の調剤業務にとって必要不可欠なツールです。薬歴は、薬学を通じて患者さまを理解するための情報源であり、患者さまから収集された情報を精密に記録することで、きめ細かな薬学的管理の実践が可能となります。
一方で、薬歴の記載方法や活用の仕方を、体系的に学ぶ機会は限られていることでしょう。
本書は、薬学管理に必要な患者さまの生活象をどのように把握し、患者さま固有の背景を言語化するためには、どのような視点が必要なのかについて解説した、薬歴作成のための指南書です。実践的な知識を得るために必要な薬歴の書き方や薬歴の活用法を網羅的に学ぶことができます。
なお、本書は2024年9月に改訂版が出版されており、電子薬歴や薬機法改正に対応するとともに、診療ガイドラインなどを最新の情報にアップデートしています。
2:しくじり処方提案 薬物治療のよくある落とし穴(花井雄貴)

- 著者:花井雄貴
- 出版社:じほう
- 発行年:2022年
医療従事者の学習スタイルの1つに、省察的実践と呼ばれる方法論があります。省察(せいさつ)とは、自分自身をかえりみて、その良し悪しについて考えることです。省察的実践では、経験から仮説を立て、その仮説を検証しながら省察を行います。
省察のような振り返り学習において、「失敗」体験は極めて重要です。「失敗は成功のもと」といわれるように、失敗体験を丁寧に省察し、成長の糧にしていくことで、薬剤師の専門性を高めることができるからです。
本書は、経験豊富な薬剤師が、処方提案における自身の失敗体験を紹介し、薬物療法のピットフォールを丁寧に解説したものです。実際の臨床現場において、避けられる失敗は可能な限り避けるべきでしょう。本書を活用することで、省察的実践を紙面上でシミュレーションできるように思います。
3:一緒にトレーニング!薬剤師・薬学生のためのEBM活用法と論文の読み方(上田昌宏)

- 著者:上田昌宏
- 出版社:金芳堂
- 発行年:2023年
EBM(Evidence-Based Medicine)とは、1.疑問の定式化、2.情報収集、3.情報の批判的吟味、4.情報の患者さまへの適用、5.1~4のフィードバックという5つのステップで構成される医療従事者の行動スタイルです。EBMはエビデンス(医学論文)そのもののことではなく、エビデンスの使い方に関するフレームワークともいえるでしょう。また、EBMの実践において参照される情報の多くは、臨床医学に関する論文です。
しかし、英語で書かれた医学論文に対して苦手意識をもつ薬剤師も多いかもしれません。本書は、医学論文を読んだことがない、あるいは医学論文を検索したことがない薬剤師にとっても、容易に読み進められるよう配慮されたEBM実践の入門書です。
仮想症例をベースに、医学論文の基本的な読み方から、論文の検索方法、統計データの活用の仕方まで、丁寧に解説されています。医学論文の活用法について、何から学べばよいか悩んでいる薬剤師におすすめです。
4:薬の上手な出し方&やめ方(ジェネラリストBOOKS)(矢吹拓)
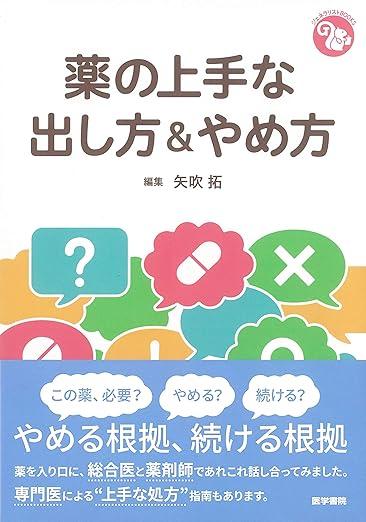
- 著者:矢吹拓
- 出版社:医学書院
- 発行年:2020年
診療ガイドラインの多くは、「どのような状況で薬物治療が推奨されるか?」といった疑問の解消に役立つ一方、「どのような状況で薬物治療の中止が検討できるか?」といった疑問に対して、明確な回答を与えてくれません。また、薬物治療の中止や処方薬の減量に関して、具体的な方法や論拠を学ぶ機会は限られているように思います。
しかし近年では、潜在的に不適切な薬物療法に対する関心が高まっており、薬剤師の業務においても、処方されている処方薬の減薬や減量提案をする機会は多いでしょう。
本書は、薬物治療の中止や処方薬の減薬に関する基本的な考え方や具体的なノウハウをまとめたものです。大きく2部構成となっており、前半はポリファーマシー(多剤併用)状態にある仮想症例をベースに、薬物治療に関する医師と薬剤師のディスカッションが言語化されています。
後半では、薬物治療に対する専門医の考え方がまとめられており、治療を続ける根拠、中止する根拠について、体系的に学ぶことができます。
5:薬剤師のための医薬品情報のトリセツ(菅原鉄矢)
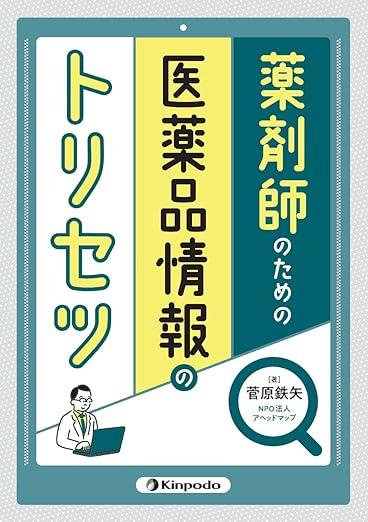
- 著者:菅原鉄矢
- 出版社:金芳堂
- 発行年:2023年
薬剤師にとって、医薬品の添付文書は、最も身近な医薬品情報といえるかもしれません。また、診療ガイドラインや薬剤師向けのウェブサイトなどを活用しながら、医薬品に関する情報を収集している薬剤師も多いでしょう。
加えて、本記事でも紹介しているような薬剤師向けの専門書、あるいはEBMの実践で参照される医学論文も、医薬品に関する有用な情報源となり得ます。このように、医薬品に関する情報といっても極めて多様であり、その活用方法も異なります。
膨大な医薬品情報を前に、どのような情報をどのように収集し、どのように活用すればよいのか思い悩んでしまうこともあるでしょう。
添付文書に記載されている情報で問題が解決しない場合、次に参照すべき情報は何でしょうか。そんな疑問や悩みの解消に役立つのが本書です。
医療現場で直面する「わからないこと」に対する向き合い方のノウハウが詰まっています。
薬剤師が持っておくべき【無料スマホアプリ7選】
キャリアアップをしたい薬剤師におすすめの本
6:抗菌薬の考え方,使い方 ver.5 コロナの時代の差異(岩田健太郎)
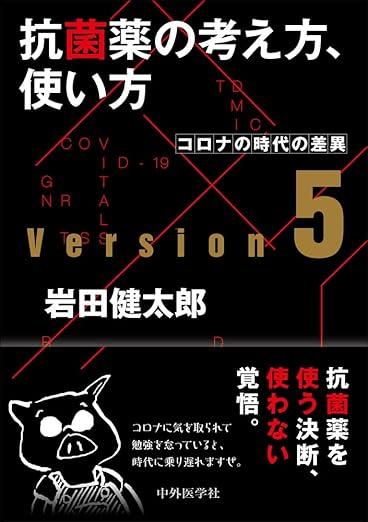
- 著者:岩田健太郎
- 出版社:中外医学社
- 発行年:2022年
抗菌薬の種類は豊富であり、その治療対象となる感染症の原因菌も多様です。抗菌薬の薬理作用を熟知していたとしても、その知識だけで臨床的に意味のある抗菌薬の使い分けが理解できるわけではありません。抗菌薬の薬物動態学的な特性はもちろん、感染症に固有の病態、適用可能な菌種など、考慮すべき要素は膨大だからです。
本書は、感染症そのものではなく、抗菌薬に焦点を当て、その臨床的な考え方や使い方を網羅的に解説しています。抗菌薬を使用するにあたり、どのような根拠で、何を目的に使うのかについて、極めてクリアに論じられています。
本書を読むことで、抗菌薬の処方に対して、なんとなく抱いていた違和感や問題意識が明確になることでしょう。
なお、本書は2022年にver.5が出版されており、新型コロナウイルス感染症に対する治療に関して、情報のアップデートがなされています。
7:調剤と服薬指導がわかる小児科これだけ(原島知恵/山本佳久/島﨑学/藤田友紀)
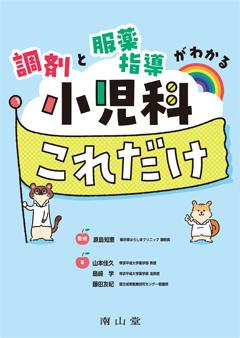
- 著者:山本佳久/島﨑学/藤田友紀(監修:原島知恵)
- 出版社:南山堂
- 発行年:2023年
小児科領域の薬物療法は、一般的な成人を対象とした薬物療法に比べて、用法用量の個別性が高く、服薬アドヒアランスに対する柔軟な配慮が求められます。また、同じ薬剤成分でも、シロップ剤や顆粒剤など、剤形の相違も多く、調剤の手技も多様です。
小児科の処方箋を応需した経験が少ない薬剤師にとって、このような薬物療法の多様性を体系的に経験、学習できる機会は限られていることでしょう。
本書は、小児科で取り扱う医薬品の調剤方法から、剤形の特徴、服薬指導に対する考え方に加え、臨床で遭遇する頻度の高い小児疾患と、基本的な薬物療法まで解説されています。
また、それぞれの疾患について、服薬指導のポイントのみならず生活指導において留意すべきポイントも整理されており、実践的な内容となっています。
8:腎機能に応じた投与戦略(向山政志/平田純生/中山裕史/竹内裕紀/門脇大介)
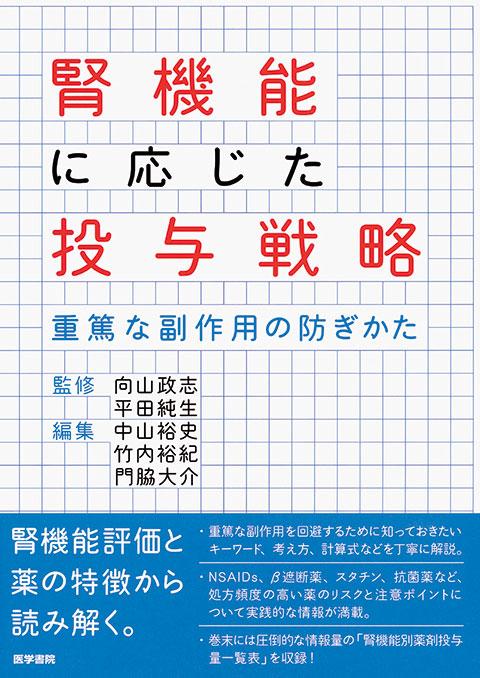
- 編集:中山裕史/竹内裕紀/門脇大介(監修:向山政志/平田純生)
- 出版社:医学書院
- 発行年:2016年
薬は、肝臓で代謝を受ける肝代謝型薬物と、腎臓から排泄される腎排泄型薬物に分けることができます。肝臓での薬物代謝は、遺伝多型などの先天的な要因の影響を受けやすく、肝代謝型薬物の用法用量を、薬剤師が単独で提案することは難しいかもしれません。
一方で、腎排泄型薬物の体内動態は、腎機能を適切に評価することで、精度の高い用法用量の提案が可能です。
一般的に、腎機能は加齢に伴い低下します。高齢化が進む現代日本において腎機能に応じた薬物治療の提案は、薬剤師にとっても重要な業務の1つです。
本書は、薬物療法における腎機能の影響を体系的に整理したうえで、診療科別に腎機能に応じた薬物療法の考え方を解説しています。高齢者薬物療法とかかわることが多い薬剤師にとって、必須の知識といえるでしょう。
9:妊娠と授乳 改訂3版(伊藤真也/村島温子)
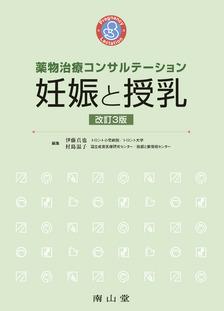
- 編集:伊藤真也/村島温子
- 出版社:南山堂
- 発行年:2020年
妊娠中の薬物療法は、胎児に与える薬の影響を精密に評価する必要があります。また、授乳中の薬物療法においても、乳児に与える薬の影響は軽視できません。
一方で、妊娠中・授乳中の女性を対象とした臨床試験が実施されることは稀であり、有害事象リスクを評価するためのデータは限定的です。
臨床試験の実施に当たっては、倫理的な観点から、副作用の検証を行うことができません。それゆえ、胎児や乳児に与える健康上のリスクを臨床試験で検討することは困難なのです。
しかしながら、実際の臨床現場においては、妊娠中や授乳中の患者さまに薬物治療が必要となるケースも存在します。限られた安全性情報をもとに、どのようなリスク評価や意思決定を行えばよいのか、思い悩んでしまうことも多いでしょう。
本書は、妊娠・授乳中の薬物療法に関する標準的な教科書です。添付文書だけでは得られない情報やノウハウが詰まった本書は、臨床現場で即戦力となる実践的な内容となっています。
【若手薬剤師必見】勉強方法や継続のコツを解説!おすすめの参考書やスマホアプリも紹介
先輩薬剤師が薦めるおすすめ本を読んで、スキルアップを目指しましょう
薬剤師として知識を身につけるためには、添付文書やインタビューフォーム、疾患のガイドラインなどをしっかりと学ぶことが基本です。
一方で、学んだ知識を現場で活かすには、幅広い方面で活躍している先輩薬剤師の経験や考え方を知ることも重要です。
また、本を読むことで自分の視野が広がり、もっとレベルアップしたい思いが沸いてくるかもしれません。それは忙しい日々のモチベーションに繋がり、人によっては今の職場から環境を変える選択肢も出てくるでしょう。
後悔のないキャリアを歩めるよう、本記事でおすすめした書籍も参考に、スキルアップを通じて薬剤師としての可能性を広げていきましょう。

監修者:青島 周一(あおしま・しゅういち)さん
2004年城西大学薬学部卒業。保険薬局勤務を経て2012年より医療法人社団徳仁会中野病院(栃木県栃木市)勤務。(特定非営利活動法人アヘッドマップ)共同代表。
主な著書に『OTC医薬品どんなふうに販売したらイイですか?(金芳堂)』『医学論文を読んで活用するための10講義(中外医学社)』『薬の現象学:存在・認識・情動・生活をめぐる薬学との接点(丸善出版)』