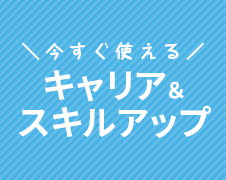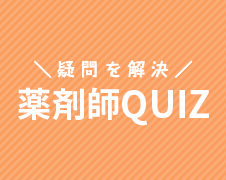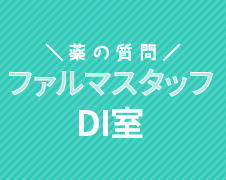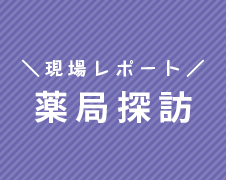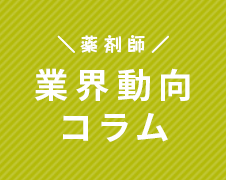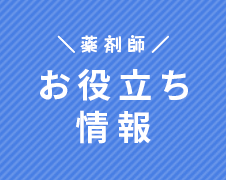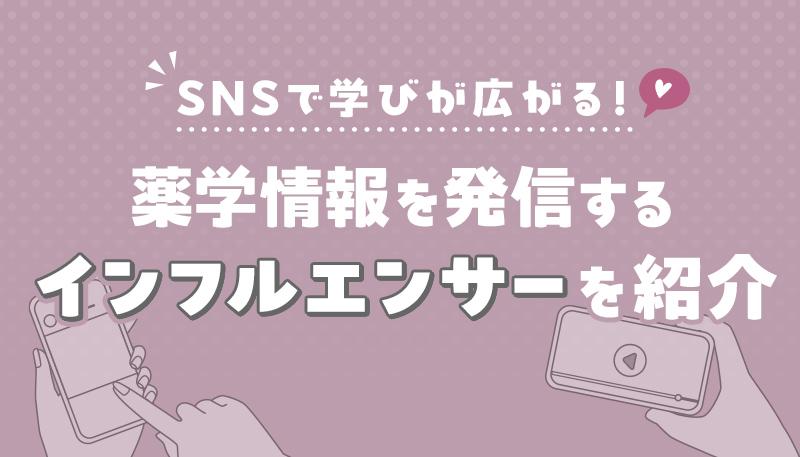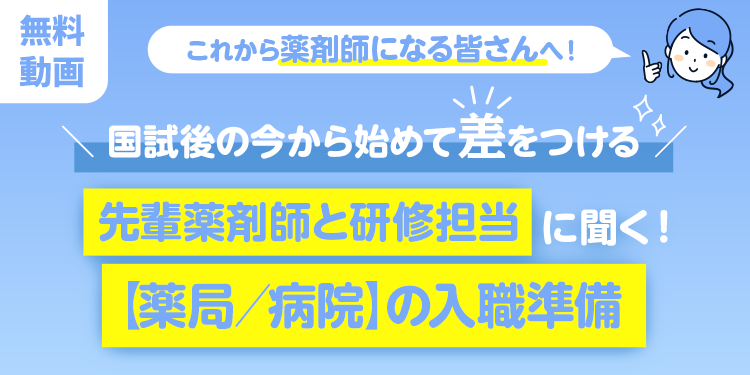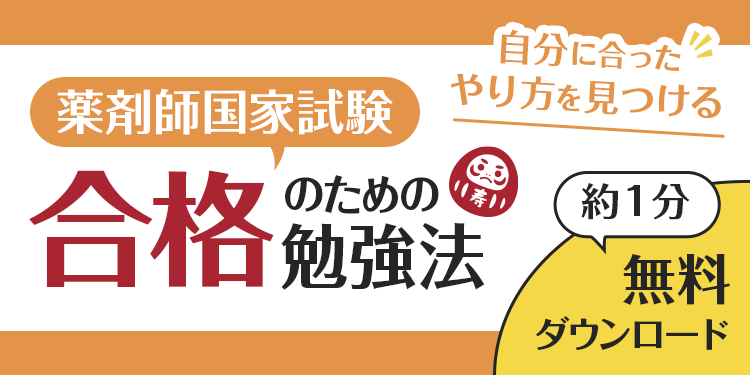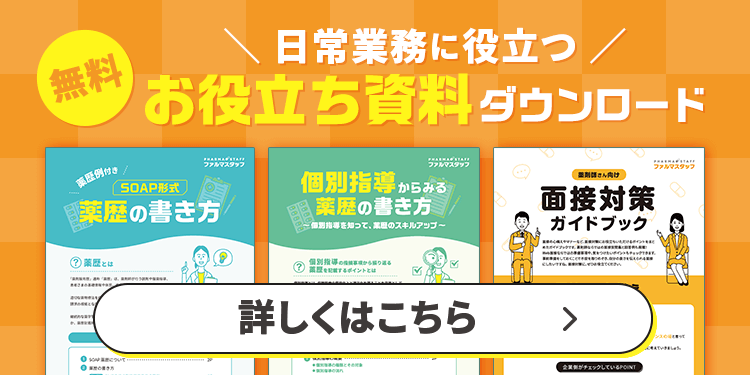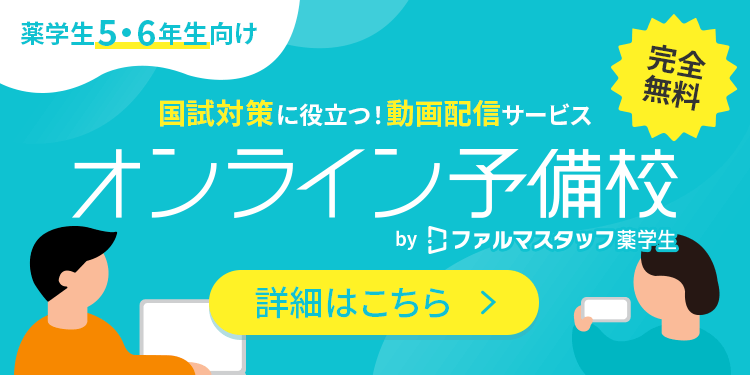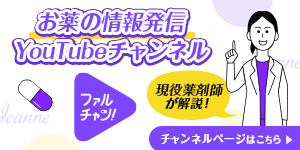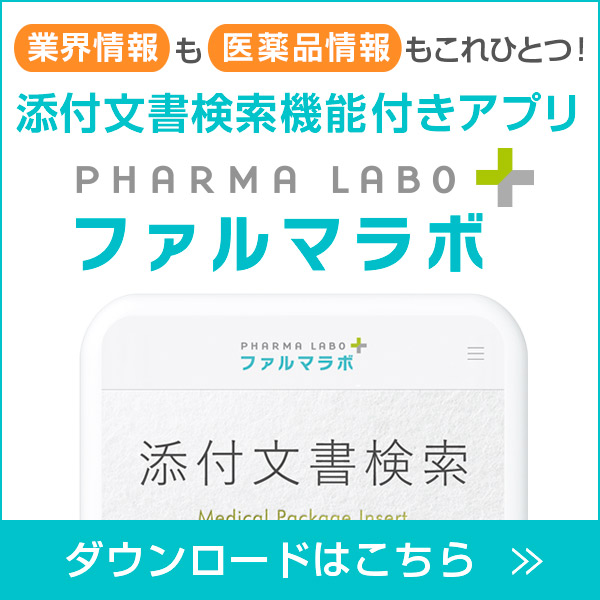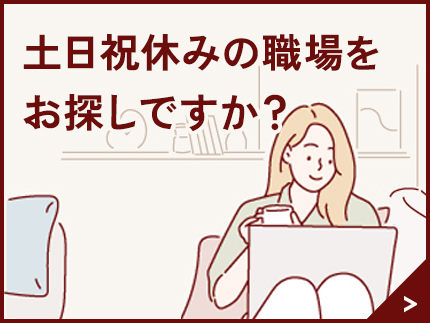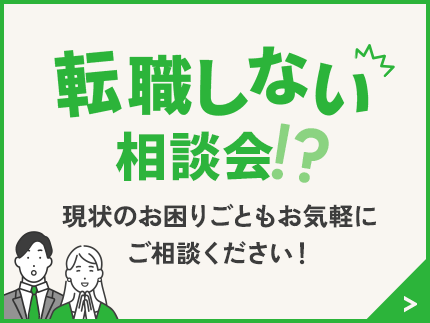- 公開日:2025.03.19
糖尿病薬の内服薬と注射薬の一覧を紹介!種類や特徴について服薬指導のポイントも合わせて解説

糖尿病の治療に用いられる薬の種類は豊富です。単一の成分だけではなく、複数の成分を組み合わせた配合剤もあります。加えて、薬によって作用機序や用法用量も異なります。そのため、患者さまの服薬負担も少なくありません。
糖尿病は生活習慣病の1つです。高齢化が進む現代では、糖尿病治療薬を内服している患者さまも数多く存在しています。近年では、糖尿病に関する新薬も登場しており、薬剤師としても新たな情報を学びながら知識をアップデートしていく必要があるでしょう。
本記事では、糖尿病の治療に用いられる内服薬や注射薬の種類や特徴について解説します。また、服薬指導のポイントをまとめているので、糖尿病の治療薬について知識を深めたい薬剤師の方は、ぜひ参考にしてください。
糖尿病に関する現状と薬を使用する重要性
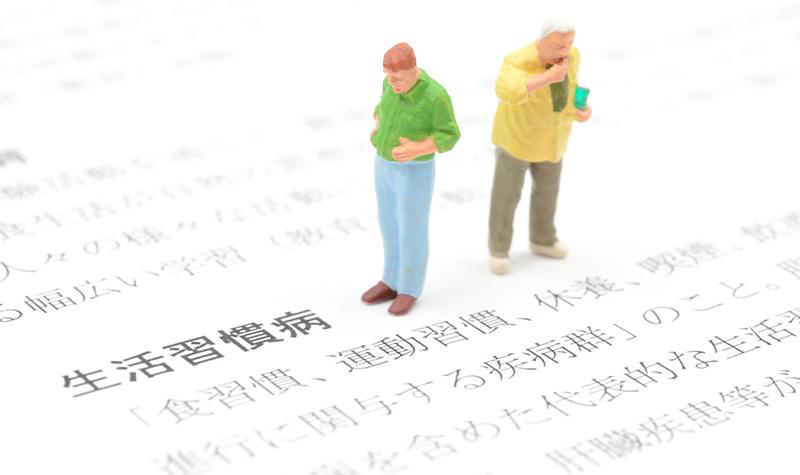
糖尿病の患者さまは、世界中で増加し続けています。まずは、日本の糖尿病に関する現状と、糖尿病の薬を使用する重要性についておさらいしていきましょう。
日本における糖尿病患者の総数と現状
糖尿病は、具体的な有病者数を把握することが難しいとされていますが、様々な調査や推計によって、その規模をある程度把握することができます。令和5年の厚生労働省のデータ(国民健康・栄養調査結果の概要)によると、「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、男性が16.8%(946人中)、女性が8.9%(1,226人中)となっています。年齢が高くなるにつれて糖尿病の割合が増加する傾向があるため、高齢化が進む現代では、今後も糖尿病患者数は増加していくと考えられます。
日本では糖尿病を重要疾患として位置づけています。健康増進法においても国民の健康を維持するための方針が明記されており、健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(健康日本21)」では、以下の対策が推進されています。
- 生活習慣の改善に重点を置いた対策
- 糖尿病合併症の予防
- 症状の進展等、重症化の予防に重点を置いた対策
これらの取り組みにより、糖尿病の予防と管理が国家レベルで進められています。
糖尿病の薬を使用する重要性
糖尿病に対する国の政策方針において、治療を継続する患者さまを増やすことや、血糖コントロール不良の患者さまを減らすことなども目標とされています。
しかし、糖尿病患者さまや糖尿病予備軍と呼ばれる患者さまの場合、適切な治療を受けていない、もしくは治療を自己判断で中断しているケースも少なくありません。
糖尿病の治療においては、継続的な血糖コントロールが重要です。生活習慣の改善だけではなく、必要に応じた血糖降下薬の使用も重要です。糖尿病に関連する合併症を予防するためにも、糖尿病治療薬の内服もしくは注射を適切に行うことが必要です。
一方で、糖尿病治療のための内服薬や注射薬を使用した結果、血糖値が下がりすぎたことや副作用などで治療を中断された経験のある患者さまも多いのではないでしょうか。しかし、糖尿病治療薬の種類も増えてきており、新しい治療薬や配合剤の登場で、治療の選択肢の幅も広がっています。次の章では、様々な糖尿病治療薬について解説していきます。
糖尿病の治療で使われる薬とは?種類別の薬一覧表を紹介

糖尿病の治療は、食習慣や運動習慣などの生活習慣の改善が基本です。それでも血糖コントロール不良の場合では、合併症の発症予防を目的に、さまざまな糖尿病治療薬が用いられます。
糖尿病の治療は、内服だけではなく注射も考慮できます。治療薬の大きな分類として、内服薬の経口血糖降下薬、注射薬のインスリン製剤およびGLP-1受容体作動薬の3つに分けることができます。代表的な糖尿病の治療で使われる薬の種類について、それぞれ詳しく紹介していきます。
経口血糖降下薬の一覧
経口血糖降下薬の種類は豊富であり、下記のように分類することができます。
| 分類 | 小分類 | 名前 |
| インスリン分泌非促進系 | ー | ・SGLT2阻害薬 ・ビグアナイド薬 ・チアゾリジン薬 ・α-グルコシダーゼ阻害薬 |
| インスリン分泌促進系 | 血糖依存性 | ・DPP-4阻害薬 ・GLP-1受容体作動薬 ・イメグリミン |
| 血糖非依存性 | ・速効型インスリン分泌促進薬 ・スルホニル尿素薬(SU薬) |
上記のように分類されるものの、各成分を組み合わせた配合剤が処方されることもあります。例えば、SGLT2阻害薬とDPP-4阻害薬の配合薬であるカナリア配合錠(テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物)やスージャヌ配合錠(シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L -プロリン)などが存在します。そのため、実際の治療に用いられる経口血糖降下薬の種類はさまざまです。
それぞれの薬の特徴を下記で紹介していきます。
SGLT2阻害薬
SGLT2阻害薬は、近位尿細管においてブドウ糖を再吸収するSGLT2の働きを阻害する薬です。近位尿細管でのブドウ糖の再吸収を減らし、尿糖として排出することで、血糖値を下げる効果が期待できます。
一方で、SGLT2阻害薬には利尿作用があり、脱水を起こしやすい患者さまには注意して投与する必要があります。特に、血糖コントロールが極めて不良の糖尿病患者さま、高齢者、利尿剤を併用している患者さまでは脱水の兆候に留意する必要があります。また、SGLT2阻害薬は、尿路感染症の発症リスクを高めることが知られています。
ビグアナイト薬
日本で使用可能なビグアナイド薬は、メトホルミン(メトホルミン塩酸塩)とブホルミン(ブホルミン塩酸塩)です。肝臓に作用して、糖の生成を抑える効果が期待できます。また、ビグアナイド薬には食欲の抑制効果も期待されており、肥満を伴う患者さまへ処方されることもあります。
ただし、肝機能や腎機能が低下している患者さまの場合、乳酸アシドーシスをきたす可能性があるため、使用が禁忌、もしくは注意が必要です。
チアゾリジン薬
チアゾリジン薬は、骨格筋と肝臓でのインスリン抵抗性を改善し、相対的にインスリンの作用を高めることで血糖値を抑える効果が期待できます。
チアゾリジン薬は、単体でインスリンの分泌を促す薬ではない点から、単独使用で低血糖が出現するリスクが少ない傾向にあります。一方で、ほかの血糖降下薬との併用時は、相対的にインスリンの作用を高める可能性があり、低血糖に注意が必要です。
α-グルコシダーゼ阻害薬
α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)は、食べ物に含まれる糖質の分解や消化を妨げることによって、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。α-グルコシダーゼ阻害薬と糖質が小腸内に同時に存在する時に効果が期待できるため、必ず食前の服用が必要です。
一般的に、α-グルコシダーゼ阻害薬による血糖降下作用は緩やかであり、高い効果を期待するには、食事療法と運動療法を怠らないようする必要があります。
DPP-4阻害薬
食事摂取時に、小腸や十二指腸から分泌されるインクレチンと呼ばれるホルモンに注目した薬です。
代表的なインクレチンとして、GLP-1を挙げることができます。GLP-1は血糖値依存的にインスリン分泌を促すホルモンです。しかしながら、GLP-1はDPP-4と呼ばれる酵素によって速やかに分解されてしまいます。DPP-4阻害薬は、DPP-4を阻害することで、GLP-1によるインスリン分泌作用を強め、血糖値を低下させます。
GLP-1受容体作動薬
GLP-1はインクレチンの一種です。血糖値が上昇した際に膵臓のGLP-1受容体に働きかけ、インスリン分泌を促す作用があります。また、グルカゴン分泌を抑えることで血糖値を下げる効果も期待できます。
GLP-1受容体作動薬は、GLP-1受容体に結合することで、直接的にGLP-1の分泌を促し、血糖値を下げます。
イメグリミン
ミトコンドリアへの作用を介して血糖を降下させる薬です。ブドウ糖の濃度に依存してインスリンの分泌をうながす作用と、肝臓や筋肉での糖代謝を改善する作用、2つの作用で血糖を降下させます。単独の使用では低血糖の副作用が出にくい薬ですが、スルホニル尿素薬との併用の場合は、低血糖に注意する必要があります。
速効型インスリン分泌促進薬
速効型インスリン分泌促進薬は、名前の通り、膵臓のβ細胞に働きかけてインスリンの分泌を促進する薬です。スルホニル尿素薬(SU薬)と作用機序が似ている薬でもあります。
速効型という名前のように、食前に内服することで適切な効果を得られます。食事30分以上前に服用した場合、低血糖が生じるリスクが高まるため、用法を遵守する必要があります。
スルホニル尿素薬(SU薬)
スルホニル尿素薬は、経口血糖降下薬の中で最も長い歴史があり、使用実績も豊富です。販売時期によって第1・第2・第3世代に分けることが一般的です。スルホニル尿素薬の作用機序は、速効型インスリン分泌促進薬とほぼ同じで、膵臓のβ細胞に働きかけてインスリンの分泌を促進させます。
直接的にインスリンの分泌へ働きかけるので、スルホニル尿素薬の使用においても速効型インスリン分泌促進薬と同様に低血糖に注意が必要です。
糖尿病の注射薬の一覧
糖尿病の注射薬は前述のように、インスリン製剤とGLP-1受容体作動薬の2つの種類に分けられ、インスリン製剤は不足しているインスリンを補充することで血糖値を低下。
一方、GLP-1受容体作動薬は前述の内服薬と同様に、膵臓のGLP-1受容体に作用することでインスリン分泌を促進させます。
尚、糖尿病の治療で用いられる注射薬は下記となります。
| 分類 | 小分類 |
| インスリン製剤 | ・超速効型 ・速効型 ・中間型 ・混合型 ・持効型溶解 ・配合溶解 |
| GLP-1受容体作動薬 | ・1日1回注射 ・1日2回注射 ・週1回注射 |
注射製剤は効き方によって使用のタイミングや回数が異なるため、必ず患者さまにそれぞれの使い方を理解してもらう必要があります。
「注射は使ったことがあるから」と、薬剤師の説明を聞き流そうとする患者さまもいるかもしれません。しかし、思わぬ副作用やトラブルを回避するためにも、必ず注射手技や接種回数について確認しましょう。
糖尿病診療の現状|厚生労働省
血糖値を下げる飲み薬|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター
血糖値を下げる注射薬|国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター
注射製剤一覧表|一般社団法人日本糖尿病学会
安全にご使用いただくために。服薬指導のポイント

糖尿病の薬は種類が豊富で、内服薬と注射薬を併用している患者さまもいます。
血糖値をコントロールし、合併症の予防のために重要な役割を果たしますが、低血糖を含めた副作用のリスクも伴います。
安全に患者さまへ使用していただくためのポイントを下記にまとめましたので、確認していきましょう。
食習慣や運動習慣などの生活習慣を確認する
服薬指導の際に、患者さまの食習慣や運動習慣など、生活習慣を確認しておくことも、副作用を未然に防ぐために重要です。
糖尿病管理においては、食事と運動が常に基本となるため、生活習慣に対する配慮をなくして良いわけではありません。
血糖降下作用の即効性が早い薬では、服用もしくは注射するタイミングによって、低血糖のリスクが高まります。そのため、食事状況などを丁寧に把握し、患者さまの生活習慣に合わせて、服薬のタイミングを伝えると良いでしょう。
低血糖の症状や注意点を伝える
糖尿病薬による副作用で注意すべき点は低血糖です。薬を内服するタイミングだけではなく、日頃の生活習慣や血糖値が不安定な患者さまなど、さまざまな理由で低血糖のリスクが高まります。
用法用量どおり正しく内服しているから、低血糖が起こらないというわけではありません。万が一に備え、ブドウ糖10gや砂糖20g、もしくは同等の量の糖分を含む飲料を常備しておくようにお伝えしましょう。
また、低血糖の具体的な症状について、患者さまに理解してもらう必要があります。
発汗や悪寒、手の震えなどの初期症状から、眠気やめまいなどの重症化の兆候までお伝えし、ブドウ糖を摂取しても症状が改善されない場合は、すぐに病院へ行くことをお伝えしましょう。
場合によっては救急車を呼ぶ必要があることまでお伝えできることがのぞましいです。いずれも周囲の方のサポートが必要となるケースも考えられるため、患者さまの家族にも、低血糖の症状について理解してもらう必要があります。
さらに、就寝中に低血糖を生じてしまうケース(夜間低血糖症)もあります。異常な寝汗や日中の倦怠感が持続したりなど、体調について気になることがあれば、主治医への相談を勧めましょう。
薬剤師からも積極的に、夜間の睡眠状況について確認できると良いかもしれません。
注射薬の手技の確認を行う
複数の製薬会社がさまざまな種類の注射薬を発売しており、その使い方や1日の使用回数も異なります。
「以前にも注射薬は使っていたことがあるから大丈夫」というような患者さまでも、再度手技の確認を行う必要があります。
初回使用の方は、特に何度も確認しながらしっかり使用方法について理解いただく必要があるため、必ず一人ひとりの患者さまに時間をかけて使い方や効果を理解いただけるように努めましょう。
シックデイについて説明する
糖尿病の方は、免疫機能が低下する傾向にあり、感染症を発症しやすいことが知られています。また治療中に感染症による発熱や嘔気、嘔吐などの消化器症状によって、食事を十分に摂取できない状態をシックデイと呼びます。
シックデイで食事量が減っているにも関わらず糖尿病治療薬を使用すると、低血糖のリスクが高まることもあります。
そのため、シックデイの対応について、処方医から指示を受けた患者さまに対してどのような説明がされたかも確認しましょう。
特にインスリン治療中の患者さまの場合、食事を摂取できなくても自己判断でインスリン注射を中断してはいけません。
発熱や嘔吐などの消化器系症状が強い場合は、必ず医療機関を受診するように指導しましょう。
患者さまが安全に薬を使用できるように糖尿病の薬について理解を深めておこう
記事内では、日本における糖尿病の現状、治療薬、服薬指導のポイントを紹介しました。
糖尿病の薬は種類も多く、薬剤ごとに作用機序も異なります。また、併用することで副作用のリスクが高まる恐れもあります。
そのため患者さまに対して、正しい薬の使用方法を伝えることはもちろん、薬を安全に使用するためにも、日常生活における留意点を伝える必要があります。
薬剤師としても、糖尿病の患者さまへ適切な服薬指導ができるよう、糖尿病の薬について最新の知識を日々身につけておきましょう。

監修者:青島 周一(あおしま・しゅういち)さん
2004年城西大学薬学部卒業。保険薬局勤務を経て2012年より医療法人社団徳仁会中野病院(栃木県栃木市)勤務。(特定非営利活動法人アヘッドマップ)共同代表。
主な著書に『OTC医薬品どんなふうに販売したらイイですか?(金芳堂)』『医学論文を読んで活用するための10講義(中外医学社)』『薬の現象学:存在・認識・情動・生活をめぐる薬学との接点(丸善出版)』