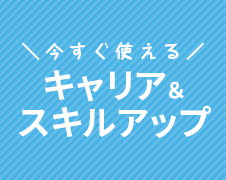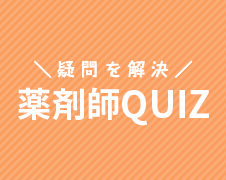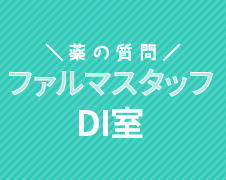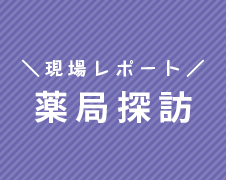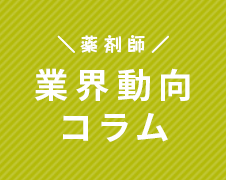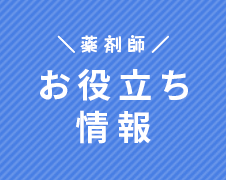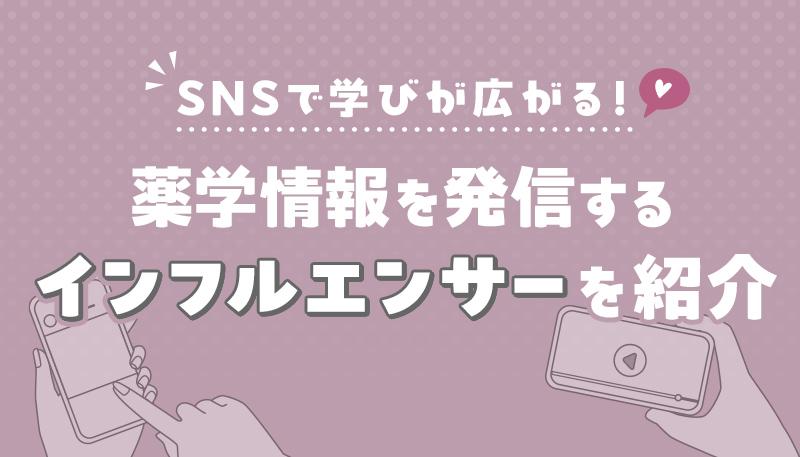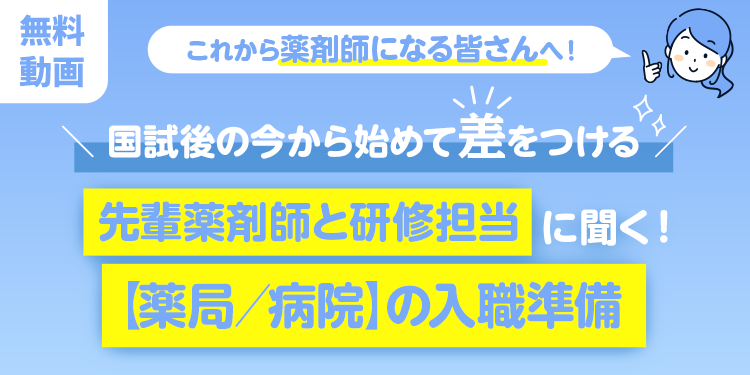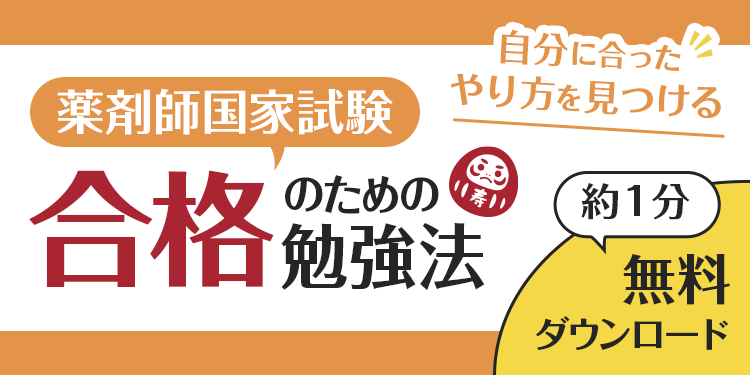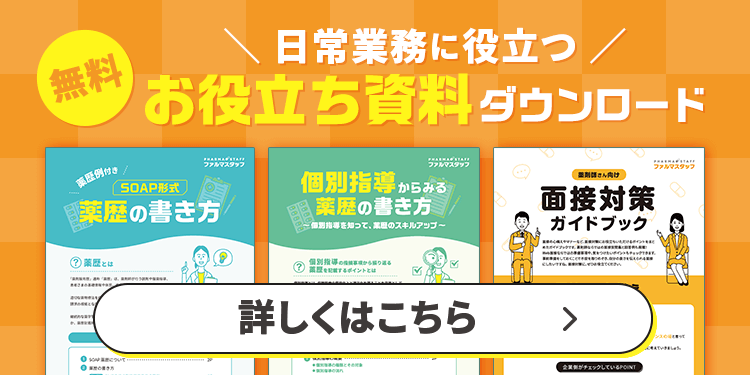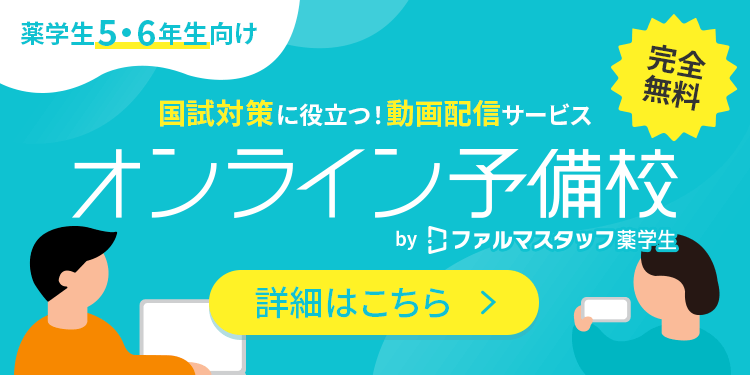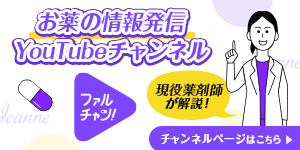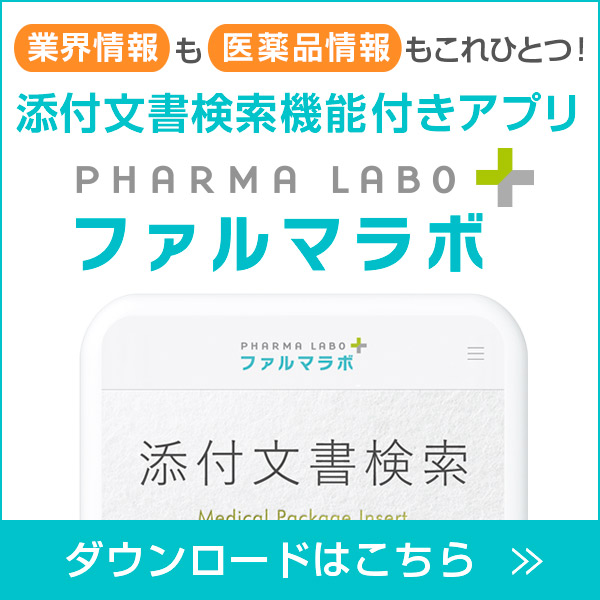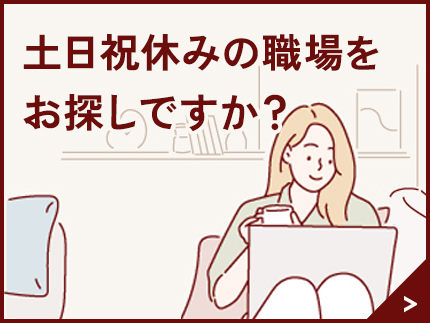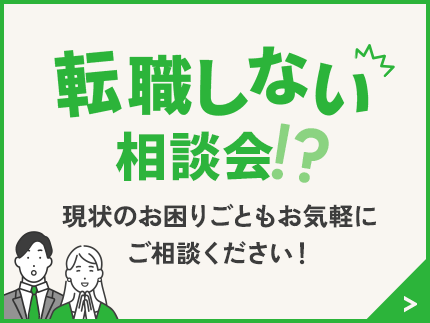|
ゾルピデム酒石酸塩は、「重篤な肝障害のある患者さま」への投与は禁忌です。肝硬変の患者さまに投与した場合、健康成人に比べてCmaxが2倍、AUCが5.3倍大きかったと添付文書には記載されています。重篤な肝障害に明確な定義はありませんが、考え方として3つの判断基準を紹介します。 1つ目の判断基準としてChild-Pugh(チャイルド・ピュー)分類があります。この分類では、グレードCなら禁忌と判断します。しかし、薬局では患者さまの状態がわからないことが多いため、この分類を活用してゾルピデム酒石酸塩の投与可否を判断するのは難しいかもしれません。 ▼Child-Pughによる分類
※各項目の点数を合計し、5~6点はA、7~9点はB、10~15点はCと分類する。 参考資料:肝炎情報センターHP「3. 肝硬変の程度の分類」| 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター 2つ目の判断基準として、CTCAE(有害事象共通用語規準)があります。これで検査値が記載された処方せんやマイナンバーと連携した特定健診情報などに記載されている肝機能の数値のいずれかがグレード3相当なら禁忌と判断します。ただし、肝機能の関連数値は上下しやすいため過去の検査値は参考にならない可能性があります。また、繊維化が進んだ肝硬変ではASTやALTが低値を示すことがあるので、数値が基準値内でも肝機能が正常とは判断できないこともあります。 ▼CTCAE(有害事象共通用語規準)によるグレード分類
参考資料:「有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳 JCOG 版」| 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター 3つ目の判断基準として、併用薬から判断する方法があります。肝硬変の治療に特徴的に使われている薬が併用薬にあれば注意します。たとえば、ウルソ( ウルソデオキシコール酸)、リーバクト、アミノレバン、リフキシマ(リファキシミン)などの併用薬があれば、患者さまに肝機能の低下がないか確認をして、用量が適切かどうか疑わしい時は疑義照会をしても良いでしょう。ただし、ウルソ( ウルソデオキシコール酸)だけを服用している患者さまは、一律に肝機能が低下している訳ではないので注意が必要です。 処方監査・服薬指導のPOINTゾルピデム酒石酸塩を処方された患者さまが高度肝障害だった場合、疑義照会をする必要があります。肝機能が低下している場合でも血中濃度が高くなる恐れがあるため、必要に応じて減量するなど注意が必要です。また、高齢者では成人に比べて血中濃度が高くなりやすいため、5mgからの開始が推奨されています。高齢者に10mgで処方されている場合、ふらつき等を確認して、副作用の兆候があれば減量を提案しても良いでしょう。参考として、他の睡眠薬では、高度肝障害のある患者さまにロゼレム(ラメルテオン)とデエビゴ(レンボレキサント)は禁忌であり、ルネスタ(エスゾピクロン)は減量する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
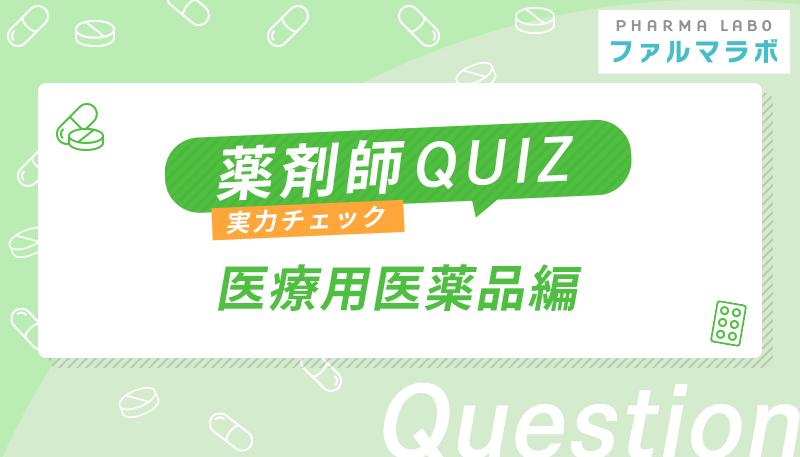
Q |
高度肝障害の患者さまに禁忌と添付文書に記載されている薬はどれでしょうか? |
掲載日: 2024/12/06
※医薬品情報は掲載日時点の情報となります
※医薬品情報は掲載日時点の情報となります